一方、石炭と水を専用の炭水車(テンダー)に積み、 本体の後ろにつないでいる機関車をテンダー機関車と呼びます。

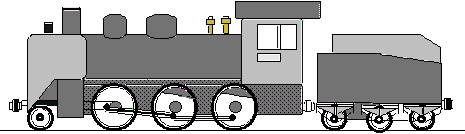
|
蒸気機関車を動かすために必要なものは「石炭」と「水」です。
機関車本体そのものに水と石炭を積んでいる機関車をタンク機関車
と呼びます。通常機関車本体の両側に水を貯める「タンク」が、
運転室の後方に石炭箱がついています。 一方、石炭と水を専用の炭水車(テンダー)に積み、 本体の後ろにつないでいる機関車をテンダー機関車と呼びます。 |
|
| タンク機関車 | 
|
| テンダー機関車 | 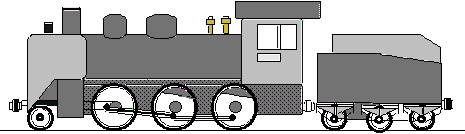
|
|
蒸気機関車は車輪(車軸)配置で分類されます。
下の表は代表的な形式と呼び方です。
表中の車軸の記号の意味は以下の通り。 | ||||||
|
| 車軸配置 | 記号 | 名称 |
|---|---|---|
| ○○○○ | 2B | アメリカン |
| ○○○○ | 1C | モーガル |
| ○○○○○ | 1C1 | プレーリー |
| ○○○○○○ | 1C2 | |
| ○○○○○ | 2C | テンホイラー |
| ○○○○○○ | 2C1 | パシフィック |
| ○○○○○○○ | 2C2 | ハドソン |
| ○○○○○ | 1D | コンソリデーション |
| ○○○○○○ | 1D1 | ミカド |
| ○○○○○○○ | 1D2 | バークシャー |
| ○○○○○○ | 2D | |
| ○○○○○○○ | 2D1 | マウンテン |
| ○○○○○○ | 1E | デカポッド |
| ○○○○○○○ | 1E1 | サンタフェ |
| ○○○○○○○○ | 1F1 | |
| ○○○−○○○ | CC | |
| ○○○○○−○○○○○ | 1DD1 |
日本の蒸気機関車の型式の付け方を統合的に定めたものとしては、明治42年(1909年)が最初でした。
例えば8620型は動軸数3(C形)のテンダー機関車、 9600型は動軸数3(D形)のテンダー機関車であることがわかります。この規定は昭和3年(1928年)に下記のように改定されました。
例えばC58(写真下)は動軸数3のテンダー機関車であることがわかります。 
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||